過去に、(株)ハードリングの軍師:
岡漱一郎様がメイン講師で
「孫子とランチェスター」勉強会は
開催したことはあります。
私自身もすごく勉強になりました。
有り難うございました。
![48cb3926-s[1]](https://livedoor.blogimg.jp/isakigyou/imgs/2/5/259734bf.jpg)
しかし、逆にした「ランチェスターと孫子」は、
まだまだ未熟者の私にとって、勉強会のテーマ
として、いや、このブログのテーマとしても、
余りにおこがましい気がします。
では、今回は誰の言葉をご紹介?
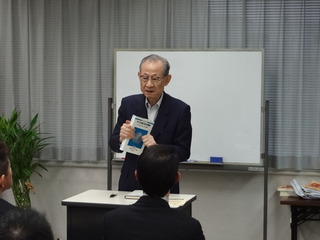
そのテーマを語れる方は、お一人でしょう。
ランチェスター経営(株)かつての教材CD
「ランチェスター・中小企業の成功戦略
/第1部 経営の基本戦略」
(現行の「戦略☆名人」の旧版)
その中から、ランチェスター法則の章で、
急に「孫子の兵法」を話題に出しています。
その一部を加筆・修正して下記にご紹介。

何か「?」だらけな終わり方ですし、
どこを決め手にするかは、それを決めるのは
読む側で違ってくるのではと思いますけど。。。


ともかく、先のような事を↑数年前の勉強会で
メイン講師を差し置いて、飛び入りで語り、
あわや乱闘になりかけたような記憶が
あるんですが・・・

そう・・・写真は語る。
岡漱一郎様がメイン講師で
「孫子とランチェスター」勉強会は
開催したことはあります。
私自身もすごく勉強になりました。
有り難うございました。
![48cb3926-s[1]](https://livedoor.blogimg.jp/isakigyou/imgs/2/5/259734bf.jpg)
しかし、逆にした「ランチェスターと孫子」は、
まだまだ未熟者の私にとって、勉強会のテーマ
として、いや、このブログのテーマとしても、
余りにおこがましい気がします。
では、今回は誰の言葉をご紹介?
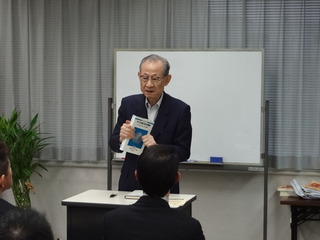
そのテーマを語れる方は、お一人でしょう。
ランチェスター経営(株)かつての教材CD
「ランチェスター・中小企業の成功戦略
/第1部 経営の基本戦略」
(現行の「戦略☆名人」の旧版)
その中から、ランチェスター法則の章で、
急に「孫子の兵法」を話題に出しています。
その一部を加筆・修正して下記にご紹介。

第2章 ランチェスター法則
その6.ランチェスター法則の経営への応用
ランチェスターの法則から、戦いのやり方には
「優勢軍の戦略」と、「劣勢軍の戦略」の
2種類あることが導き出されました
その原則を経営に置き換えると、
「優勢軍の戦略」すなわち「強者の原則」は、
1.間隔戦的商品を選び
2.間隔戦的販売地域を選び
3.間隔戦的売り方を選ぶ
ということになります。
これに対して、「劣勢軍の戦略」すなわち
「弱者の原則」は、
1.一騎打ち戦的商品を選び
2.一騎打ち戦的販売地域を選び
3.一騎打ち戦的売り方を選ぶ
ということになります。
この2種類の戦略の根本的な原理と、
その違いを完全にマスターすることが
できれば、あとはその応用ですから
「社長の術」の上達は早くなります。
ランチェスター法則自体は戦略ではありません。
この法則を、個人レベルの勝ち方に応用すれば
「戦術」になり、集団全体の勝ち方に応用すれば
「戦略」になるのです。
この原則はコロンブスの卵のようなもので、
言われてみると当たり前のことのように思えます。
しかし、それまでは戦いに勝つための
「勝ち方」については、個人個人の技能や
精神的な要素が重視されていました。
しかし精神的要素をいっさい排除して、
数学上の計算で勝ち負けを考えたのは、
ランチェスターが初めてだったのです。
東洋には、孫子の兵法があります。
孫子の場合、将軍の立場に立つ者の心構えや、
相手の将軍の意図を早く見抜く着眼点など、
人間的なものが多く含まれ、
それは大いに参考になります。
しかし、孫子が生きていた当時の兵器は、
射程距離の短い一騎打ち型兵器の槍が中心でした。
そのために、兵器に関してはすべて
「第1法則」があてはまります。
一方、中国大陸は広大ですから、戦場の決定は
広域戦の「第2法則」で考えています。
ですから孫子の兵法を経営に置き換えるには、
無理が生じてしまいます。
今でも、孫子の兵法を経営に応用した本は
多数出版されていますが、どれも決め手を
欠いているのは、ここに原因があるのです。
何か「?」だらけな終わり方ですし、
どこを決め手にするかは、それを決めるのは
読む側で違ってくるのではと思いますけど。。。


ともかく、先のような事を↑数年前の勉強会で
メイン講師を差し置いて、飛び入りで語り、
あわや乱闘になりかけたような記憶が
あるんですが・・・

そう・・・写真は語る。

コメント